数年前までは、プログラミングやデザイン、執筆、分析といった専門スキルは、長い時間をかけて学び、練習して身につけるものだった。
しかしAIの発展によって、そうしたスキルの価値は薄れつつある。
というより、スキルや能力の概念そのものが変わり始めていると言えるだろう。
漫画を描かずにマンガ本を出版
この変化を私は身をもって体験した。
漫画を描くスキルがないにもかかわらず、
AIを使って漫画本を出版することができた。
これまでなら、漫画家になるには絵の練習を何年も積み
ストーリーの作り方を学び、膨大な時間をかけなければならなかった。
だが今は、AIとの協働により、
アイデアとストーリーがあれば、
技術的なハードルを乗り越えて作品を
世に出せる時代になってしまった。
教育現場での変化
ある大学では「AIを使わずに課題を書いたら落第」という方針を打ち出しているという記事を今月読んだ雑誌で知った。
AIを使いこなすことが、今後の社会で必須のリテラシーになると認識され
手書きやタイピングと同様に、
AIとの協働が“基本スキル”として扱われ始めていると言えるかもしれない。
企業でのAI活用
私は今、会社に所属していないが、AIを積極的に導入している企業で働く人の話を聞いて驚いたことがある。それは昨年末のこと。
「AIを使わないと、AIを使わなかった理由を提出させられるから、それが面倒だから使わないってことをしなくなる」と言っていた。
今では、AIを日常的に使うのが当たり前になってきた。
「使っても使わなくてもいいツール」から「使うのが前提のツール」へ
と移行している現実を表している。
AIを使わないことが例外となり、その理由を説明する必要がある――
インターネットや電子メールが「使わない理由」を問われるレベルで当たり前になったように、AIもまた同じ道を辿っているようだ。
今後のスキルを考える
従来型の「手を動かす」スキルの重要性は確かに低下している。
その代わりに、AIに正確な指示を出す力、AIの出力を見極めて修正する力、そして発想力や判断力が求められるようになっているように感じる。
もうスキルはいらないというか、スキルの定義そのものが変わっている最中で、
過渡期には「最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのでもない。唯一生き残るのは、変化できる者である」という格言が
頭を過ぎる。
そして今日もAIに一問一答しながら、その変化の波の中でもがいている。
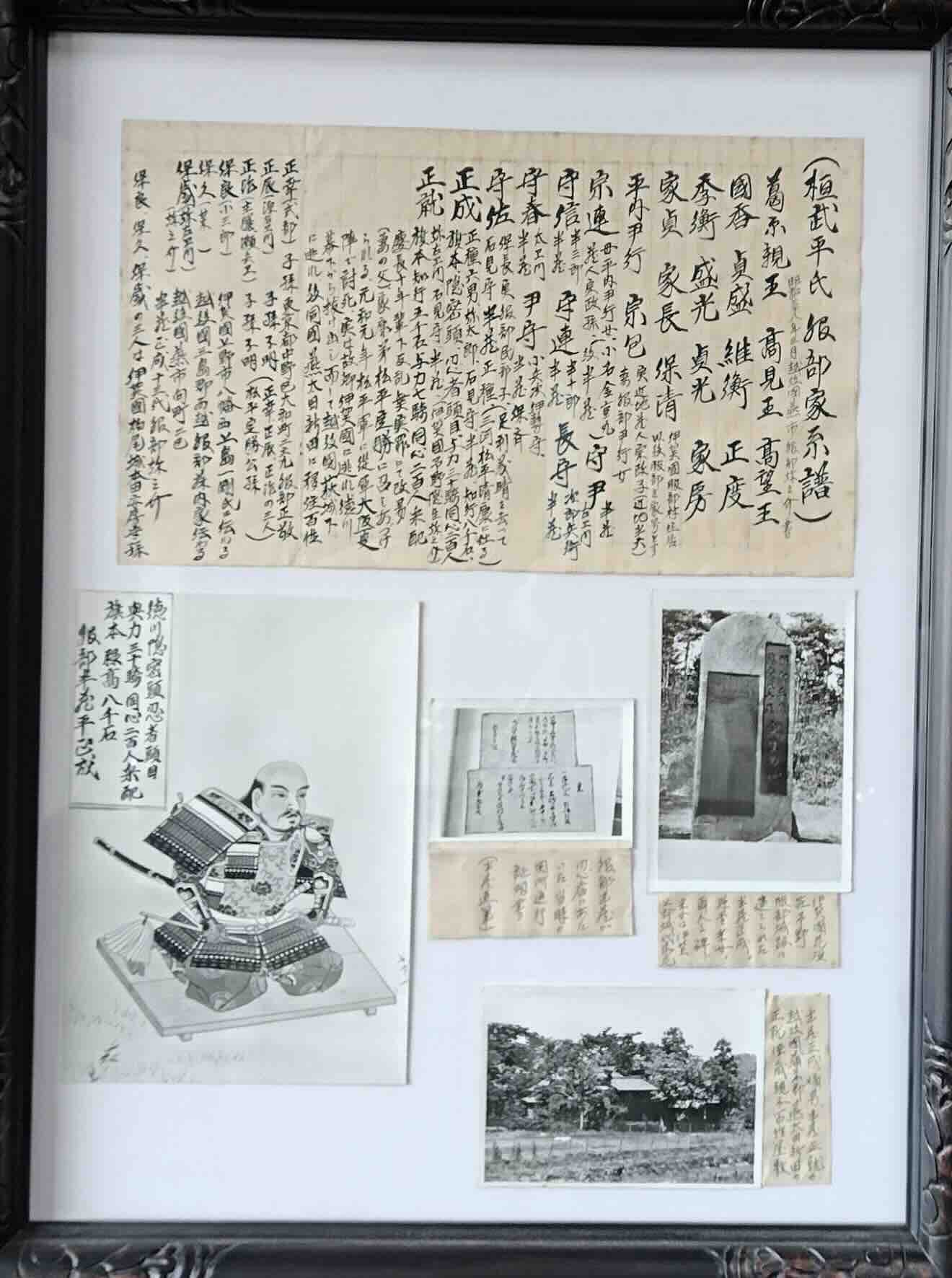
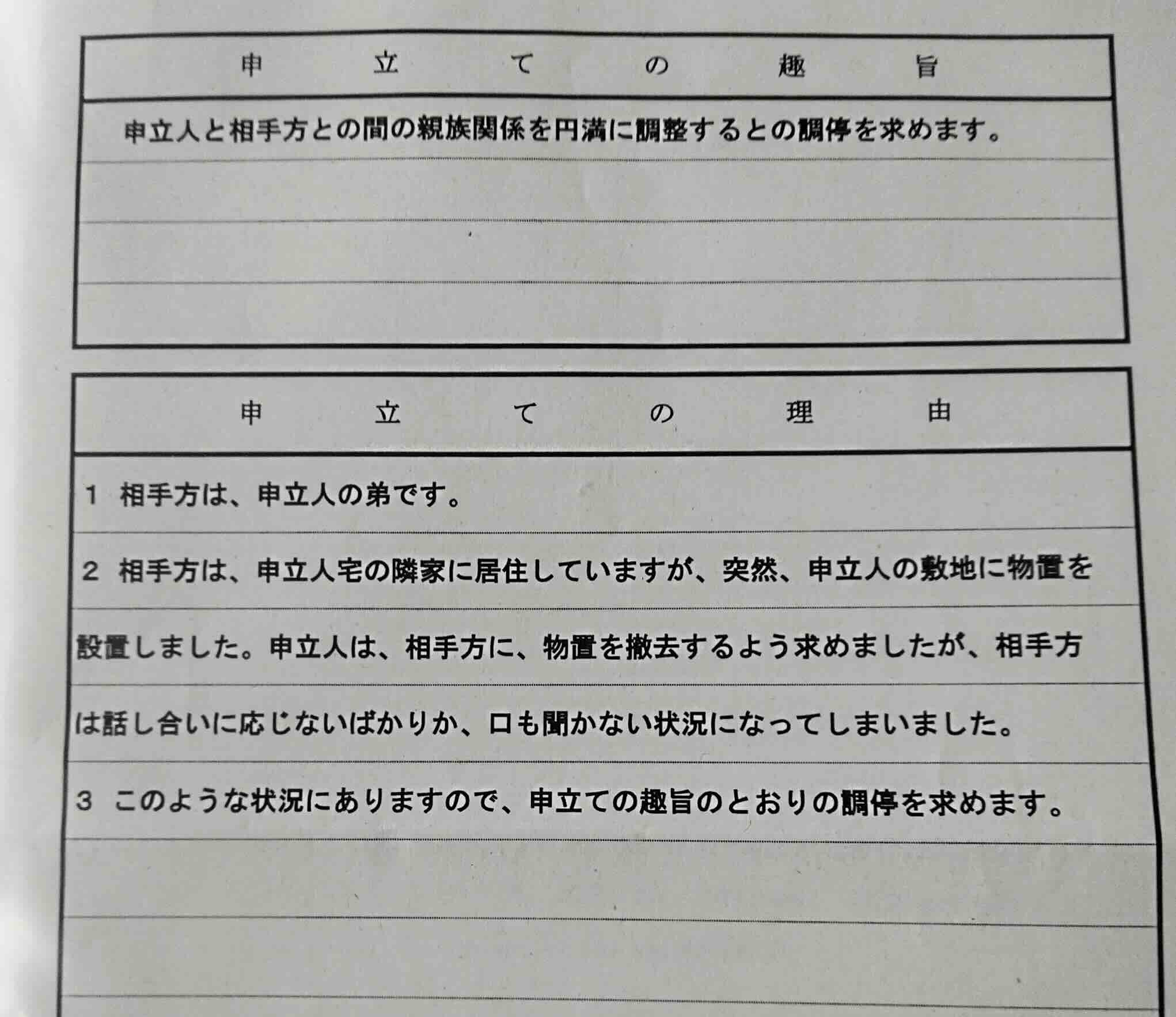

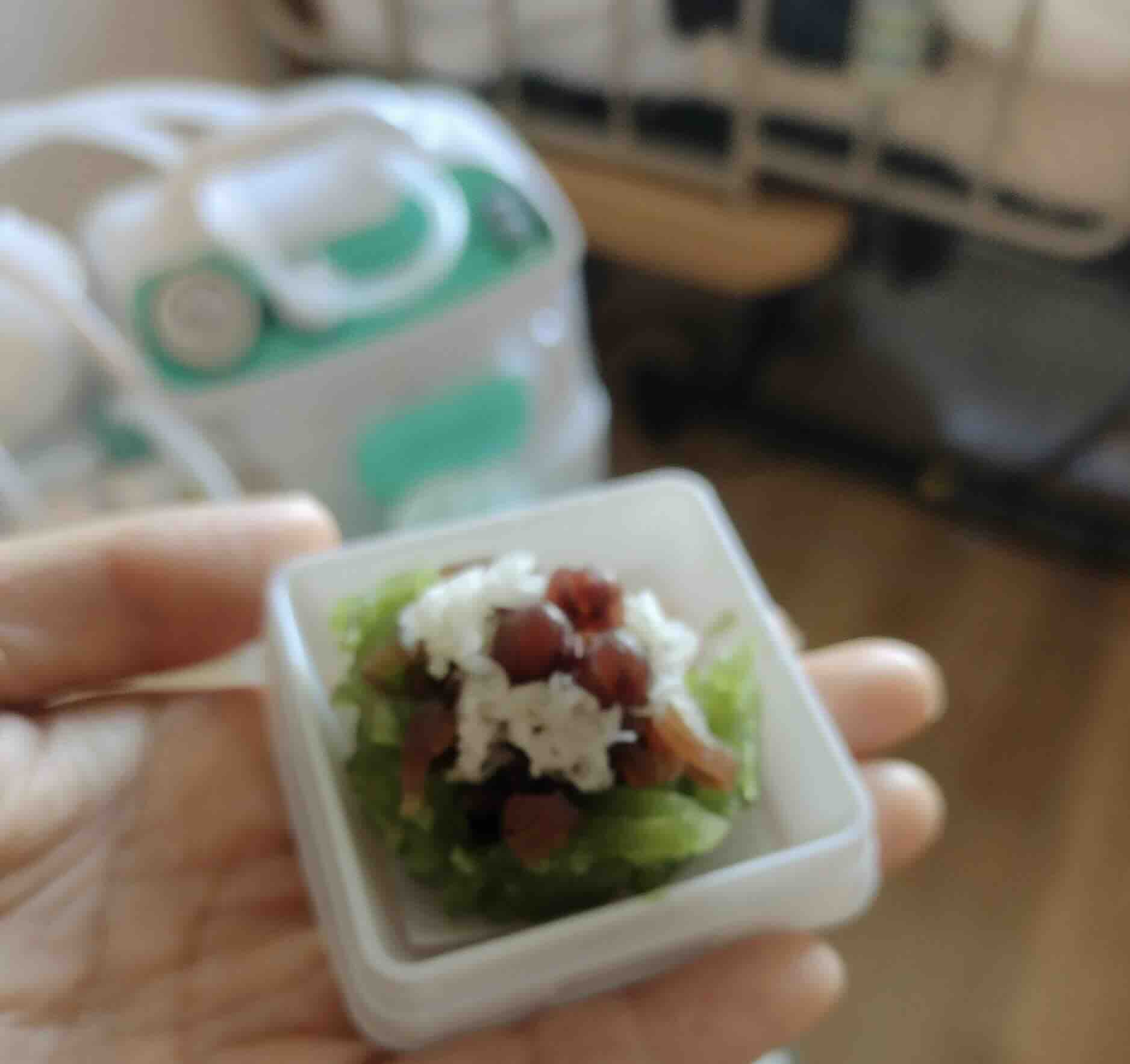
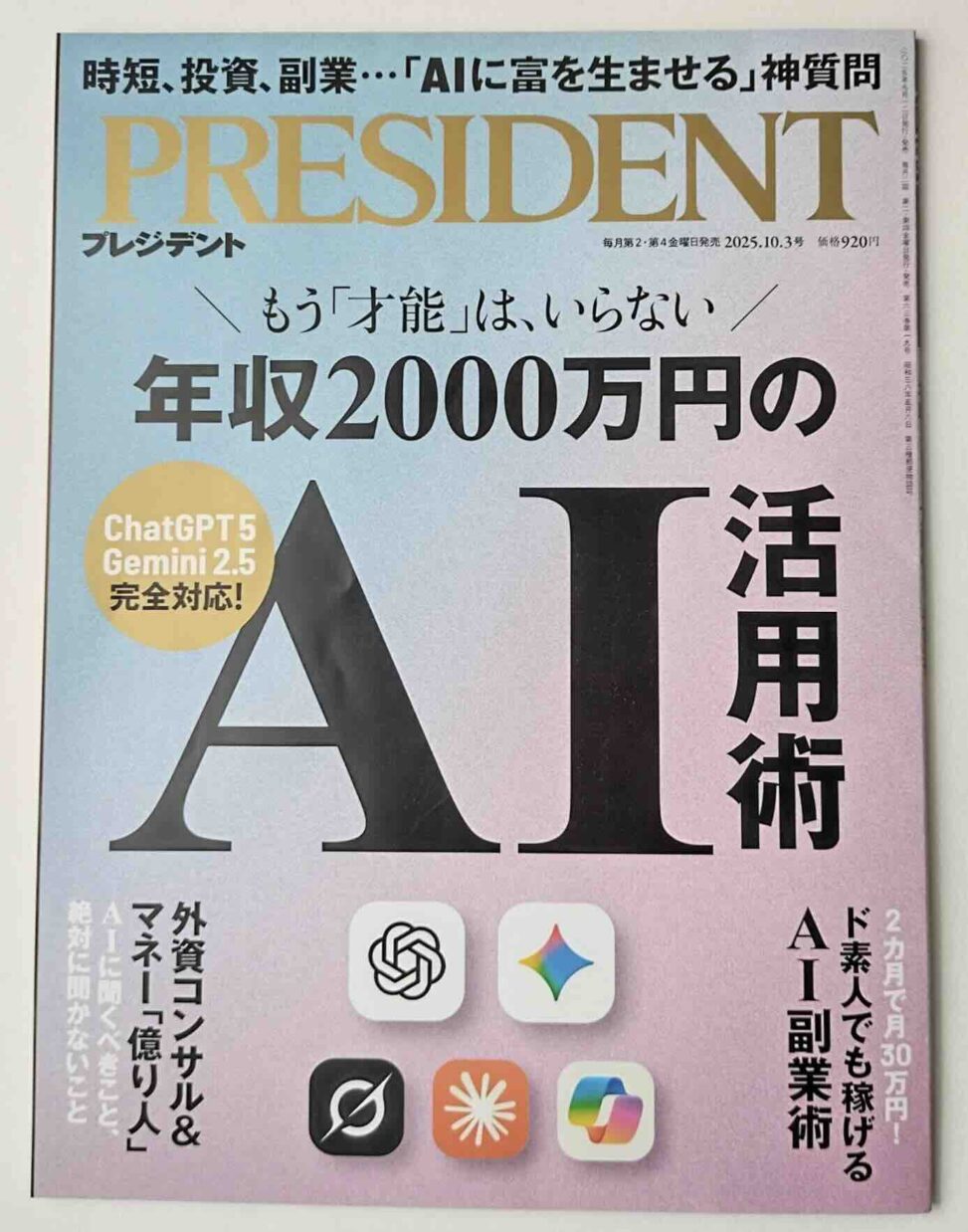
コメントを残す