初釜の茶事
それは4〜5時間に渡る参加型エンターテイメント。
遡れば平安時代から存在していたという。
待合では、初めて本当のワラで編まれた露路草鞋を履く。
これが凹凸が足にフィットせず、サイズも合わなくて
思わず「歩きヅラっ!」と心の中で叫ぶ。
その瞬間から、古の人々は一体どうしていたのかと思いを巡らせる。
現代のゴムソールのような耐久性や柔軟性はないけれど、
昔は道路がアスファルトではなく土だったから
案外藁草鞋の方が歩きやすかったのかもしれない。
飛脚のような走る仕事の人々は何を履いていたのだろう、と想像が広がる。
いや、それ以前に
着物を着付ける時点からすでに意識が古代へと向かっていた様な・・
ミシンのない手縫いの時代、直線が縫いやすいからこその構造。
直線の反物をどう立体的に着るか、
日本独特の色彩や組み合わせを見つめる中で
現代から少しずつ離れていく感覚があった。
流石に3時間を過ぎる頃には、足の痺れが限界に達する。
本当は礼儀に反するのだろうが、一度立ち上がらせてもらった。
それもまた、茶事の体験の一部として心に刻まれる。

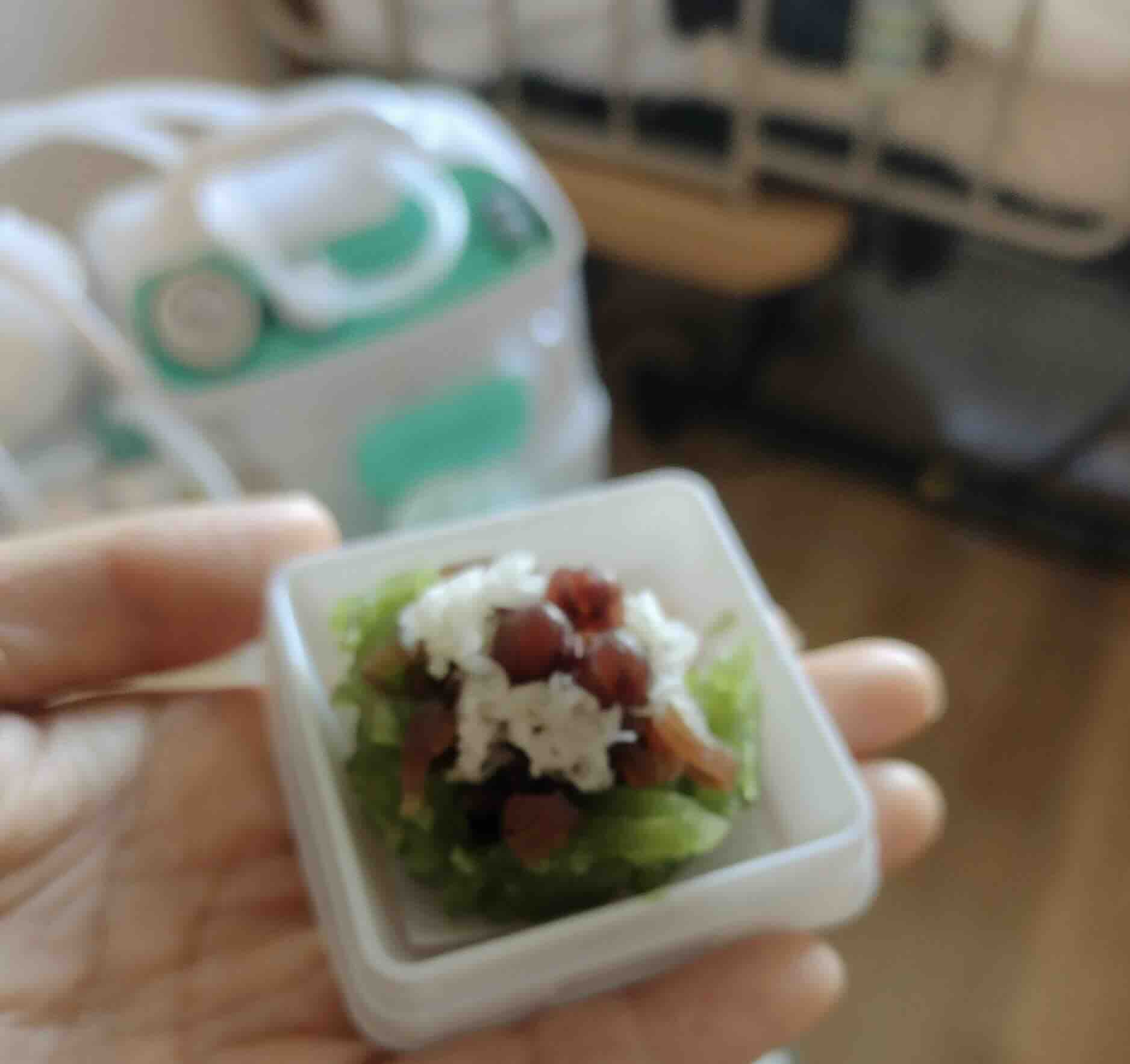

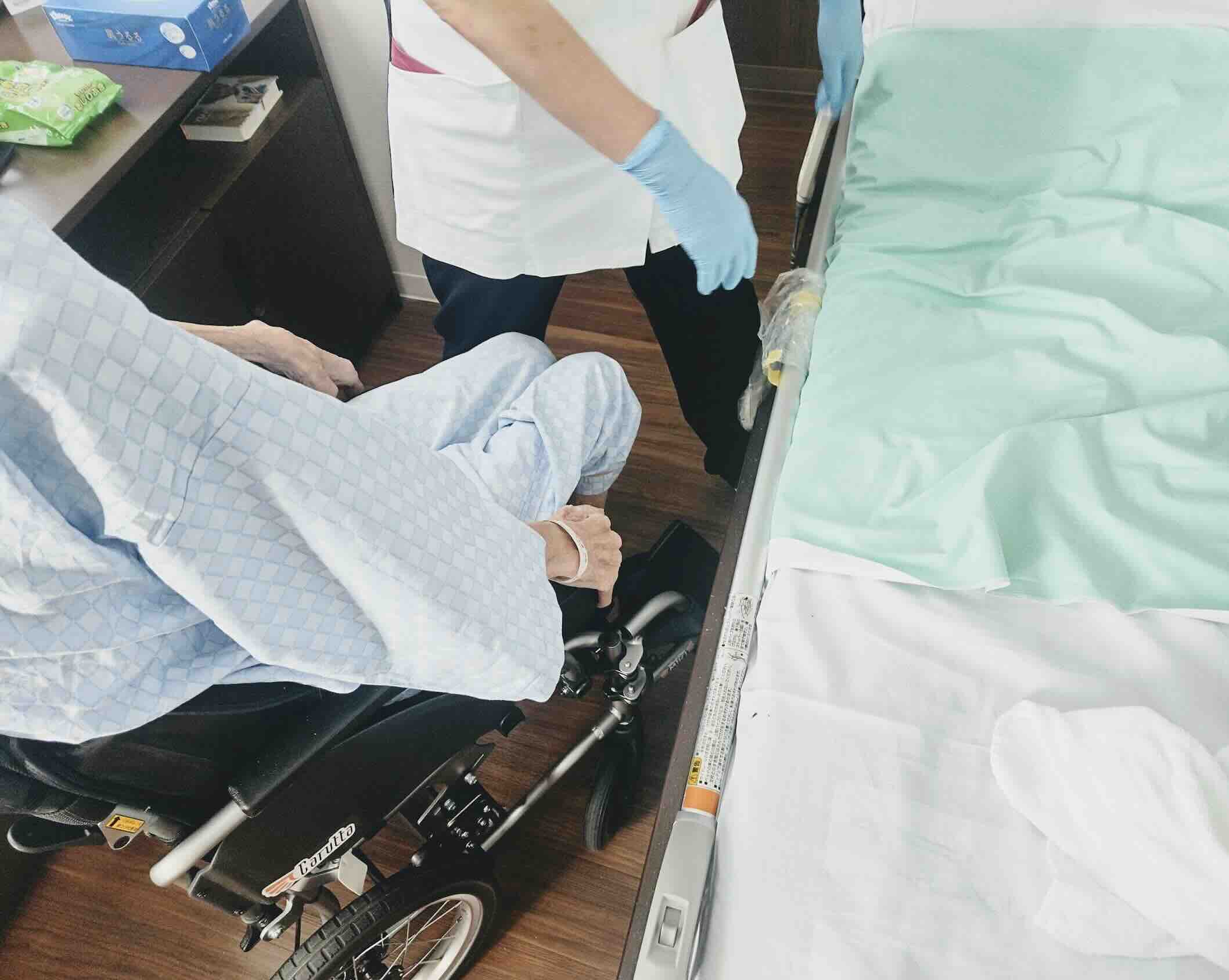

コメントを残す