茶道を学びつつ
茶道を通して歴史も学び直している。
再発見したことなどを少しまとめてみる。
茶道に根付く思想
茶道は、想像以上に多様な思想の影響を受けている。
禅、儒教、仏教、五行陰陽思想といった東洋の哲学が
その屋台骨となっているが、
さらにはキリスト教の要素まであるという説もあり、驚かされた。
歴史的背景を考えれば、細部にその影響が潜んでいる可能性もある。
例えば、茶席で使われる道具には五行(木、火、土、金、水)の要素が表現されている。
- 棚:木
- 炭火:火
- 土風炉(どぶろ):土
- 釜:金
- 釜の湯:水
また、柄杓を上向きにする(陽)ことで、
四角い棚(陰)とのバランスを取るといった精緻な配慮も見られる。
棚の構成によっても、このバランスは変わる。
茶道とキリスト教の関係
茶道の稽古ではキリスト教について語られることはないが、歴史的なつながりを示唆する仮説はいくつもある。
- 利休七哲のうち、5人がキリシタン
- 高山右近、蒲生氏郷、前田利長、牧村兵部、瀬田正忠
- また、七哲の一人である細川忠興の妻はガラシャ(細川ガラシャ)
- 千利休の息子たち(小庵、道庵)の名が、洗礼名の「ジョアン」に似ている
- 千家は大阪・堺の南蛮貿易で財を成し、外国人と接触する機会が多かった
- 千利休の切腹の原因となったとされる木像があった大徳寺
- 大徳寺で禅の修行を積み、人脈を広げた
- 天文4年(1535年)、キリシタン大名・大友宗麟が大徳寺に瑞峯院を建立
- 瑞峯院の「閑眠庭」は石組みが十字になっており、「十字架の庭」とも呼ばれる
- キリシタン灯籠もある
さらに、茶の作法にもキリスト教的な要素が見られる。
- 茶入れを拭く袱紗さばきや茶巾の扱いが、聖杯を拭く動作に似ている
- 「濃茶」の作法(ひとつの茶碗の同じ飲み口から飲む)が、ミサのワインを回し飲みする儀式に類似
- 茶室の入口「躙り口(にじりぐち)」が聖書の「狭き門」に由来する説
- 茶道具を清める際、帛紗を垂直に立て、指で横一文字を描く動作(裏千家)
- お点前に「点」という文字を使う不自然さ
こうした点を挙げるとキリがないが、決定的な証拠があるわけではないので、この辺で。
- 茶入れを拭く袱紗さばきや茶巾の扱いが、聖杯を拭く動作に似ている
- 「濃茶」の作法(ひとつの茶碗の同じ飲み口から飲む)が、ミサのワインを回し飲みする儀式に類似
- 茶室の入口「躙り口(にじりぐち)」が聖書の「狭き門」に由来する説
- 茶道具を清める際、帛紗を垂直に立て、指で横一文字を描く動作(裏千家)
- お点前に「点」という文字を使う不自然さ
こうした点を挙げるとキリがないが、決定的な証拠があるわけではないので、この辺で。
細川家の魅力
利休七哲の中でも、私は細川家に特に興味がある。
時代の流れに翻弄されながらも、知恵と決断力で危機を乗り越え
家を存続させてきた。
歴史の変遷を経てもなお存続し続けている点を考えさせられる。
この動画はとてもよくまとまっていて何度も聞きました。
細川家の美術館「永青文庫」では
茶道具や歴史的資料の展示のほか庭園でお抹茶もいただけるらしく
以前近くに住んでいた頃に
今の様な興味があったら年パスで通ったのにとちょっと悔しい。
茶道を学ぶことが
歴史を再発見するきっかけになるとは思っていなかったが
この機会に新たな視点を持ってまた学びたいものだ。

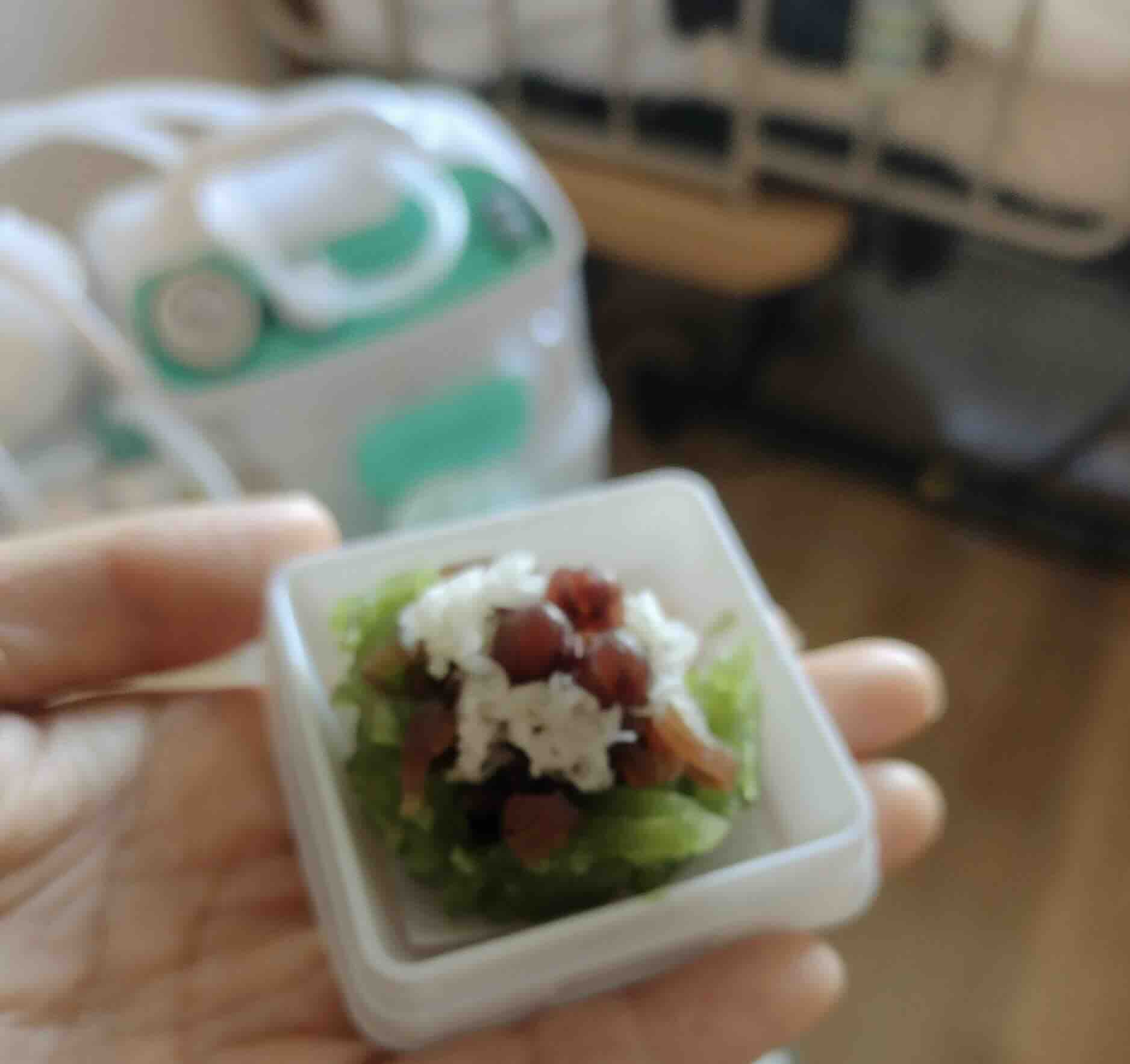

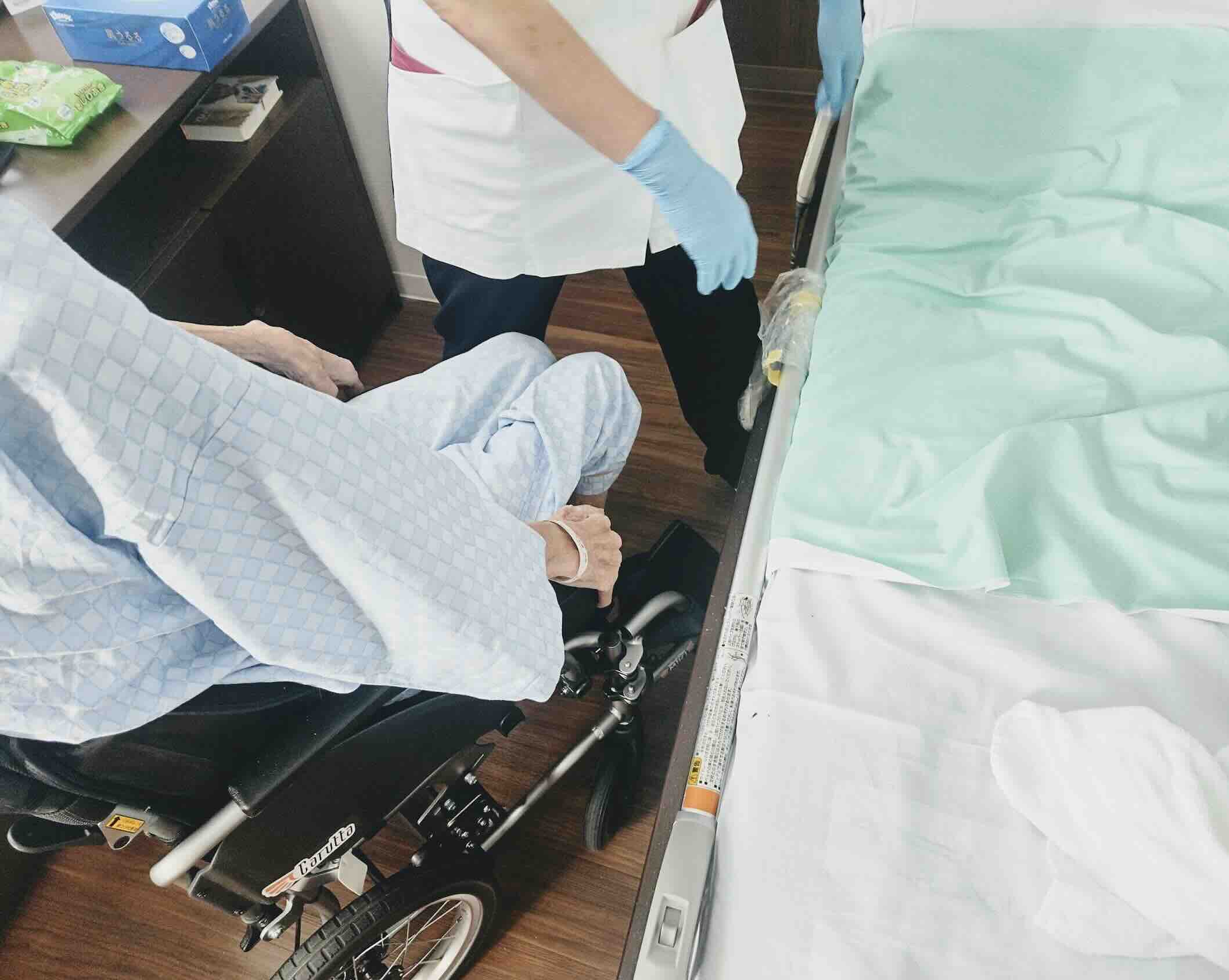

コメントを残す