高野山に行ってきた。神聖な場所というイメージを持っていたけれど、
実際に行ってみると観光地として整っていて、
少しギャップを感じるかもしれない。
奥之院では、二十万基とも三十万基とも云われる無数の供養塔が立ち並んでいる。
戦国時代の武将たちが、敵味方関係なくここで祀られているというのは大変
感慨深いと思っていた。
だが実際に目にすると、少し印象が変わった。
有名な歴史上の人物から、現代の大企業まで
多くの名前が並ぶ供養碑は、そのスケールに圧倒される。
一つ一つに込められた思いや背景はあるのだろうけれど、
どこか「存在感を示す」こと自体が目的になっているようにも感じられた。
もちろん、見る人によって受け取り方は違うけれど・・
例えば、高野山へ行くのに欠かせない南海鉄道。
その創始者のお墓。そこには「関西一の鉄道王」と書かれた立て看板があった。
確かにその称号に相応しい。でも書き方よ・・
「人々の交通に大いに貢献した」なら印象は変わっていたかもしれない。
そんな風に引っ掛かることが多々あった。
また、お土産屋では「般若湯(はんにゃとう)」という名のお酒を見つけた。
般若はサンスクリット語で「知恵」を意味し、お酒を飲むことで知恵が授かる、または知恵を深めるという考えから、「知恵のわき出る湯」という意味合いで使われ僧侶が戒律で禁じられている飲酒を、隠れて行う際に用いた言葉だとか。
高野山では、弘法大師が
「塩酒一杯これを許す」と述べたことから、
寒さをしのいだり病気を癒す目的で
お酒を飲むことが許されていたそう。
聖と俗がうまく共存してきた歴史を感じた。
高野山は、思い描いていた「聖地」という印象とは少し違ったけれど
多くの発見があった。
帰り道、私は初めて「塵になりたい」と思った。
私は、白洲次郎の「葬式無用、戒名不用」が昔から好きだったけれど
そこに自分なりの言葉として「塵となれ」を加えることにした。

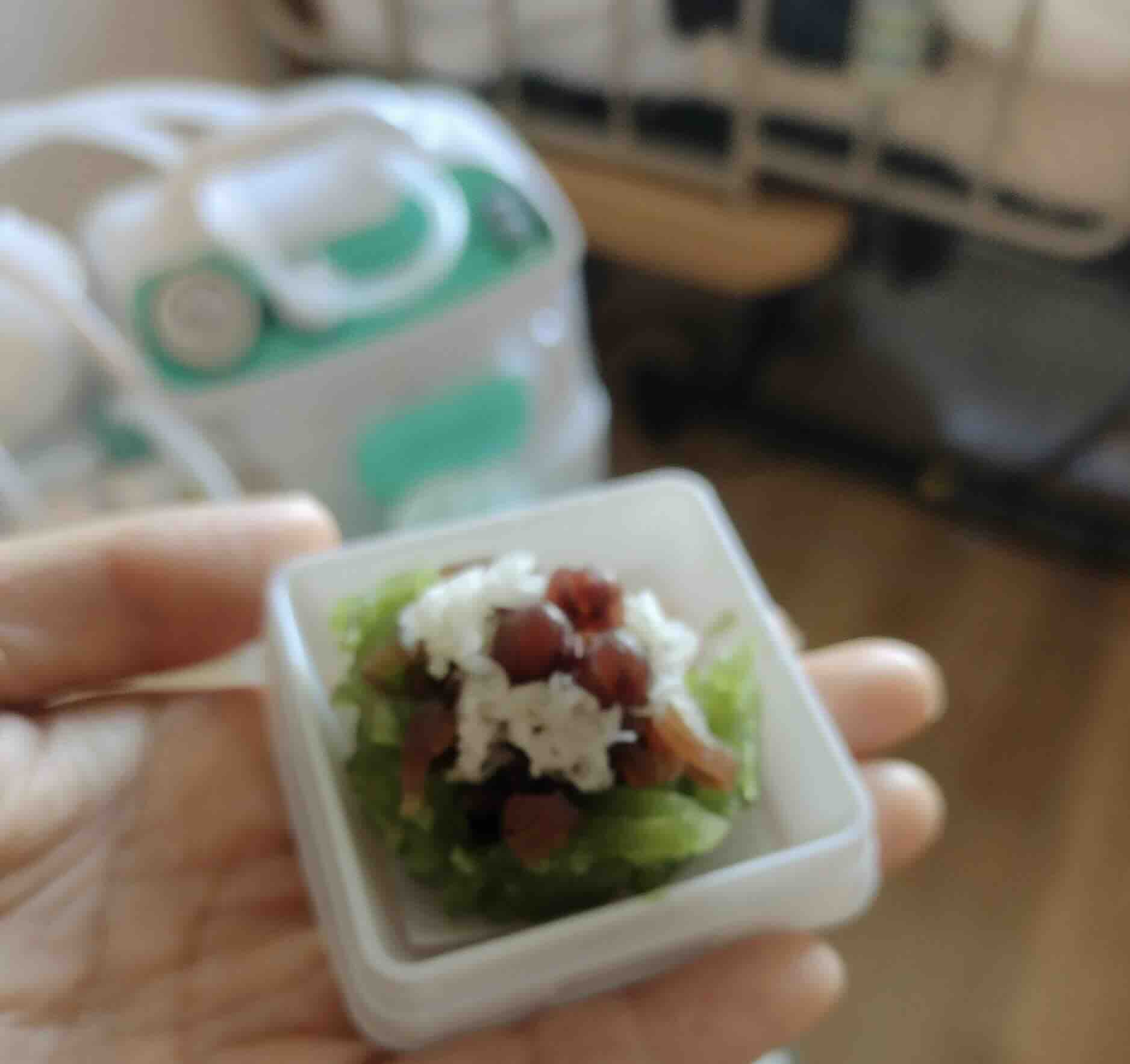

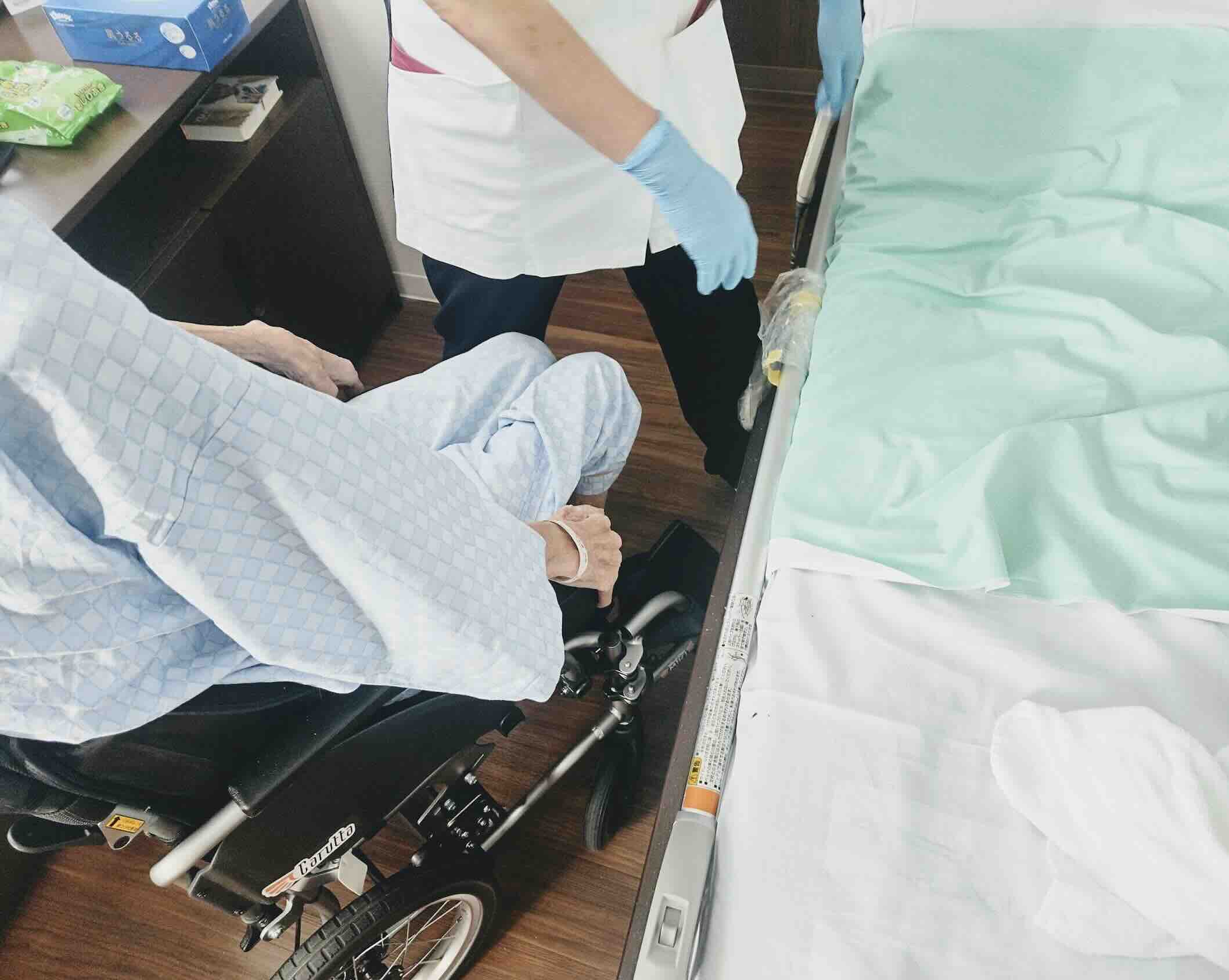

コメントを残す